今回のテーマは、「荒生秀紀さんに学ぶ!お米農家として大切な3つのこと」について解説します。
先月、友人の紹介で荒生秀紀さんとお会いする機会がありました。荒生さんは、2007年から2019年までの13年間、山形大学の農学部で無肥料・無農薬栽培について研究をしていました。今では「荒生勘四郎農場」を経営しており、山形県を代表する無肥料・無農薬栽培農家の1人です。
そんな荒生さんが、ともに大学で研究していた粕渕辰昭さんと書いた「自然との共生をめざすコメ作りー江戸時代に学ぶ新農書ー」を読んで学んだ、お米農家として大切な3つのことを紹介します。
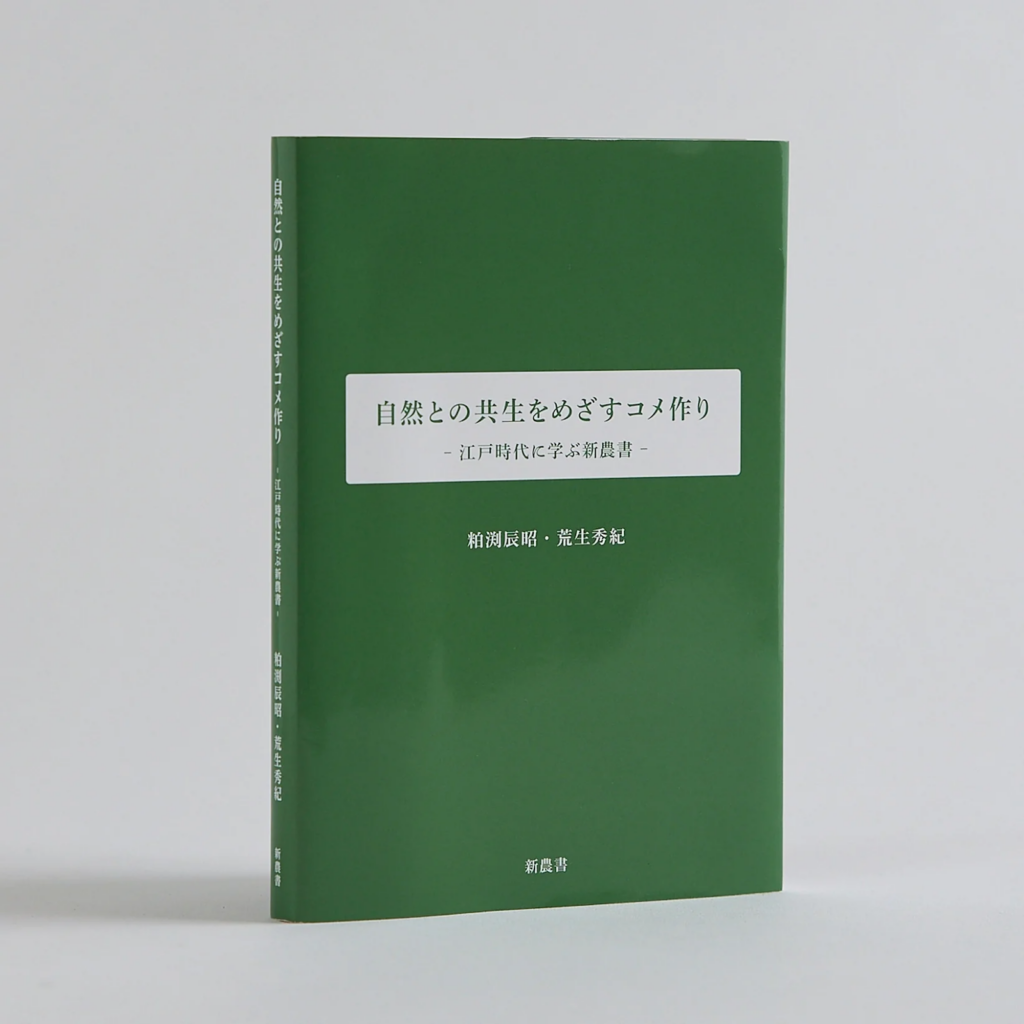
結論、お米農家として大切な3つのことは「肥料と農薬の役割を理解する」、「自分の目で見て、触れる」、「草取りは入念に行う」です。
早速こちらの3点について、順番に深堀りしていきましょう!
肥料と農薬の役割を理解する
稲作では、肥料や農薬の使用が作物の見た目を良くする重要な要素となります。見た目の良い作物は市場での評価が高くなり、消費者に選ばれやすくなります。その結果、農家の収益が増加し、得た利益を再び農業資材の購入に充てるという好循環が生まれます。
しかし、一方で「稲作には必ずしも肥料や農薬が必要ではない」という考え方もあります。なぜなら、田んぼには自己施肥機能があり、自然のサイクルによって養分が供給されるため、過剰な施肥は必要ないからです。
イネが健全に成長するためには、窒素・リン・カリウムの三大栄養素が不可欠です。特に窒素は成長を大きく左右し、不足すると収量の減少につながります。しかし、田んぼの土壌にはすでに多くの窒素が含まれており(10aあたり表層20センチ中に400kg)、追加の施肥が必ずしも必要とは限りません。
一方、畑作では事情が異なります。畑には窒素固定の手段が少なく、自然に供給される窒素量が限られています。そのため、作物の健全な生育には施肥が欠かせません。
このように、稲作と畑作では養分供給の仕組みが異なり、それに応じた適切な施肥の判断が求められます。
自分の目で見て、触れる
稲作において、肥料や農薬の適切な散布は重要ですが、それと同じくらい大切なのが、イネの生育状況を正しく把握することです。そのためには、葉色や水温を目視で確認し、必要に応じて調整を行うことが求められます。
葉色の変化から病気を見極める
イネの葉色は、その健康状態を示す重要な指標となります。例えば、葉の色が濃い緑色や紫がかった緑色になっている場合、病気の兆候である可能性が高いです。このような異変を見逃さず、早急に対策を講じることで、病害の拡大を防ぎ、安定した生育を確保できます。
水温管理でイネの生育を守る
イネは適温での生育を好むが、高温の水を嫌う性質があります。そのため、夏場などで水温が上がりすぎた場合は、新たに冷たい水を入れて温度を調整することが重要。適切な水温管理を行うことで、イネのストレスを軽減し、健全な成長を促すことができるのです。
田んぼの立地条件と整地の重要性
田んぼの管理には、立地条件の見極めも欠かせません。水を安定して確保できる環境が必要であり、特に上流に水源地があることは、安定した水供給が期待できるため理想的です。また、土の均平が整っていないと生育にムラが生じるため、整地作業を行い、±2〜3センチの範囲に抑えることが望ましいです。こうして環境整備を適切に行うことで、イネの生育を均一に保つことができます。
自らの目で確かめ、適切に対応することが成功の鍵
稲作の安定した収穫には、田んぼに足を運び、自らの目で状況を確認しながら適切な調整を行うことが不可欠です。葉色や水温をこまめにチェックし、適切な対応を取ることで、イネの健康を維持し、収量の安定につなげることができます。
このように、肥料や農薬の使用だけでなく、目視による管理を徹底し、適切な対応を行うことが、より良い稲作へとつながります。
草取りは入念に行う
「多数回中耕除草法」
これは、江戸時代の農書に記された、シーズンで繰り返し田んぼの除草作業を行う手法のことです。
多くの農書には5〜6回以上中耕除草を行うよう記されています。
この江戸時代の農書の内容は、現代でも活かせるものが存在し、草取りをすることには多くのメリットがあります。
まず、田んぼを手で掻くだけで雑草が取れるため、手軽に除草ができます。 また、肥料分が雑草に取られることがなく、これによりイネの生育が助けられます。さらには、土が柔らかくなることでイネの成長が促進され、最終的には雑草の成長が抑えられるという効果もあるのです。
草取りを始める適切な時期は、田植え後5〜20日ごろが理想的です。この時期に管理を行うことで、健康な稲作を実現することができます。
この本には、草取りについて以下のように記されています。
「良い農夫は草がまだ茂らないうちに草をとり、普通の農夫は草が茂ってから取り、草が蔓延ってもとらないのが、下下の下の農夫だ」
まとめ
今回は、お米農家として大切な3つのことを解説しました。
現代の田んぼは、地域の拡大や機械化によって江戸時代とは大きく異なっています。
しかし、イネの性質や生き物について理解することは、イネだけでなく、お米を食べる人の健康や安全につながると学びました。
書籍の10%も紹介できていませんが、農業初心者から熟年者まで幅広く学べる一冊です。
ご興味のある方はぜひ手にとってみてはいかがでしょうか。
現在、横芝光町産のお米の販売サイトを準備中です。 清潔で純粋な農産地として優れた町のお米を全国、さらには世界へ届けられるよう努力しています。 ぜひチェックしていただけると嬉しいです。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

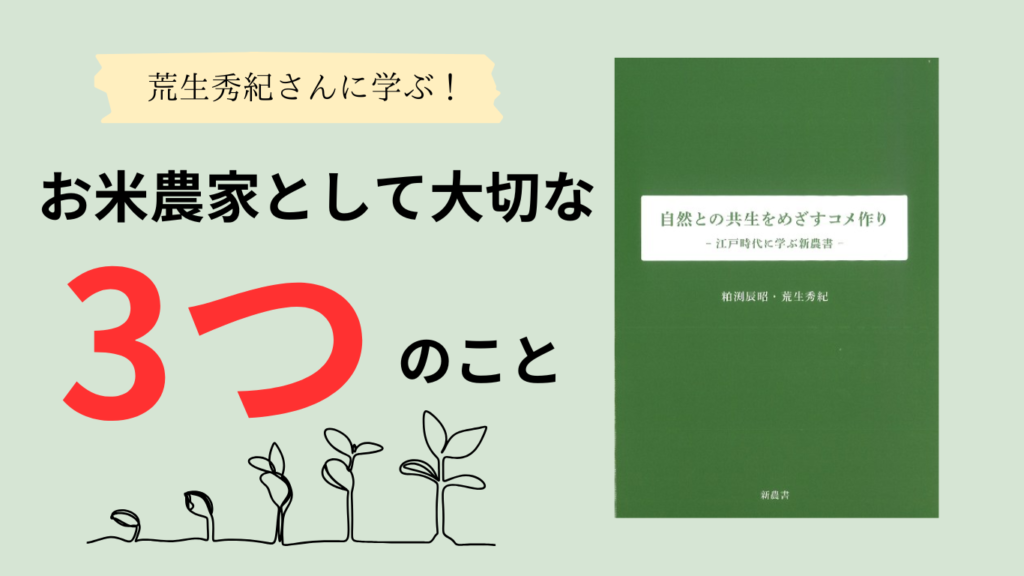

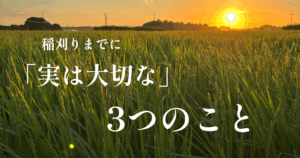






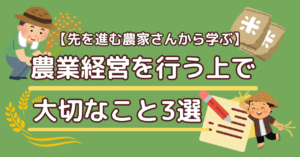
コメント