- お米作りで大切なことって何…?
- タイミングが大事って聞くけど具体的にタイミングって…?
- 実際に現場を経験してる農家さんの話を聞きたい!
農業に関する書籍は多いですが、実際のプロ農家が書いた情報もある一方で、農業を経験したことがない(知識としてあるが)人が書いたものも一部あります。
基本的に農業のことを学びたいのであれば、就農を予定してる地域や、同じ作物で経営をされてる人の意見を聞くことが、とても重要です。
それを踏まえ、今回は千葉でお米作りを3年してるShoeiが現場経験を踏まえたリアルな農作業のお話を紹介。
前回の投稿「【農業ブログ】田植機、沈む──朝から始まった「救出作戦」」では、田植機が沈みかけた経験から農業の厳しさを痛感しました。あれから約3ヶ月、僕たちの田んぼで、稲刈りが始まり、順調に育ってくれています。
田植えから稲刈りまでの約60日間、僕は毎日欠かさず作業日誌をつけ、稲の成長を見守ってきました。教科書には載っていない予想外の出来事や、長年の経験から培われた知恵が必要な場面に直面し、想像以上に多くの学びがありました。
今回の記事では、田植えから稲刈りまでの約60日間で「とくに印象に残った3つの出来事」を紹介します。
これは、インターネットや本で調べた情報ではなく、僕自身の実体験であり、50年以上農業に携わってきた祖父母の知恵が詰まった内容です。これからお米作りを始めたい方、実家の農家を継ぐことを考えている方にとって、きっと大切なヒントが見つかるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
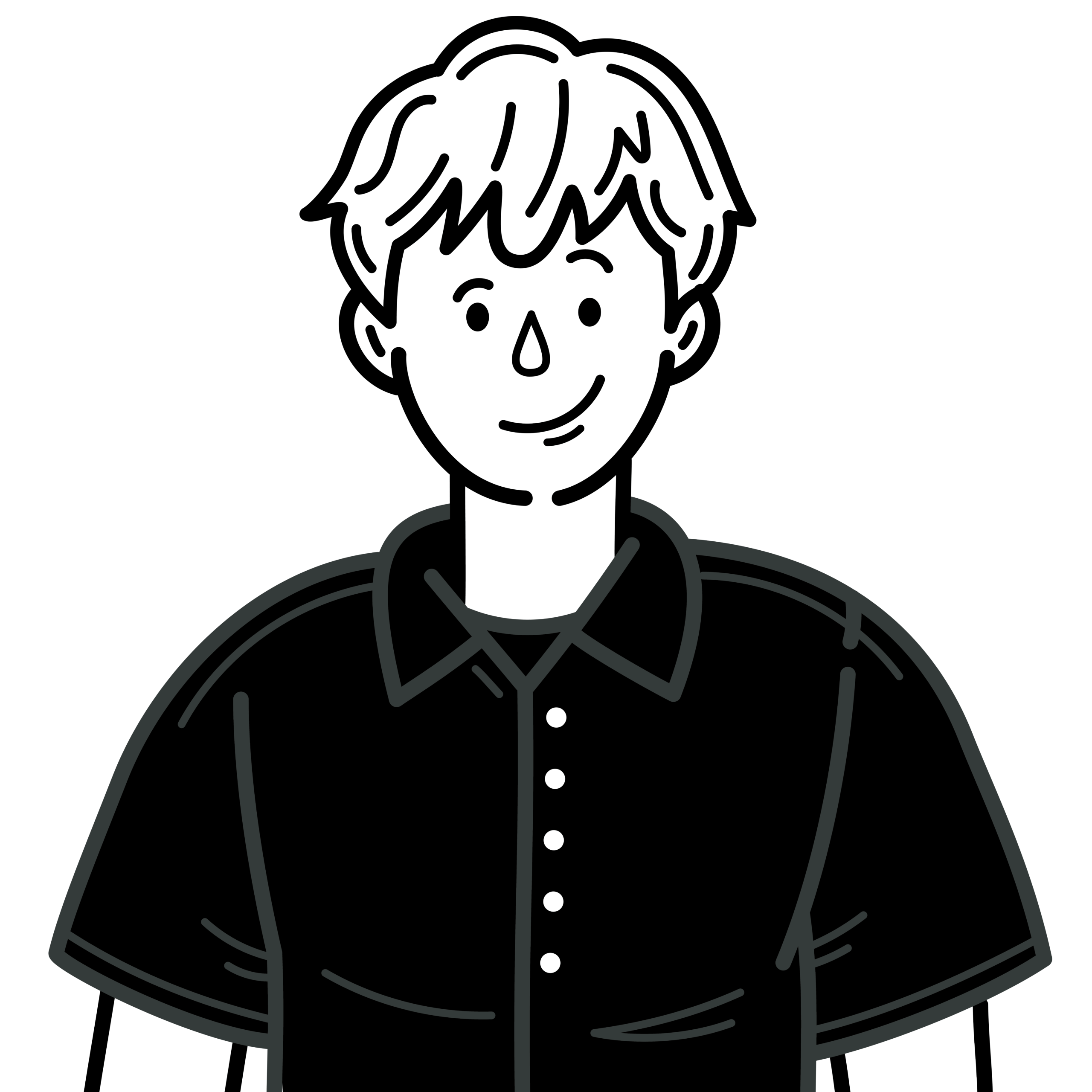
この記事を読んで「うちの田んぼではこうしてるよ!」といった経験談があれば、ぜひコメントで教えてください!
1. 猛暑との戦い!2週間で元に戻る畦畔(けいはん)の草刈り


田植え後から稲刈り直前まで、僕たちが最も多くの時間を費やした作業の一つが「畦畔(けいはん)の草刈り」でした。畦畔とは、田んぼの周りの土手やあぜ道を指します。一見、稲の成長とは関係ないように思えますが、美味しいお米を作るためには欠かせない重要な作業です。
雑草の成長スピードに驚かされる
この夏の時期は雑草の成長スピードが他の季節に比べて早いです。畦畔の草刈りを終えて2週間もすると、まるで作業をする前のような状態に戻ってしまい、作付から刈り取りまでに3回は草刈りを行いました。本来であれば、4回は行ないところでしたが、他の作業との兼ね合いもあり、3回までとしました。
作業にはウイングモアとスパイダーモアという手押しの草刈り機を使い、軽トラックに積んで田んぼを回ります。僕たちの田んぼだと、本気を出せば3日ほどで終わる作業。しかし連日の猛暑で長時間の作業が難しく、4〜5日かけてじっくりと行いました。
3回も草刈りをする理由とは?
害虫対策
畦畔の草は、カメムシをはじめとする害虫の住処になります。草むらに潜んでいるカメムシは、稲が実り始めると一斉に田んぼへ飛来し、お米の品質を大きく低下させてしまうため、稲刈り前には徹底的な草刈りが欠かせません。
風通しの確保
稲が密集している田んぼは、風が通りにくくなります。畦畔の草を刈ることで、田んぼ全体に風が通りやすくなり、稲の根元に湿気がたまるのを防ぎます。これにより、病気の発生を抑える効果が期待できます。
水の管理
田んぼへの水の出し入れは、畦畔の土手の部分で行います。草が生い茂っていると、水の流れを調整する作業がスムーズに進みません。草を刈ることで、水路の確保や水門の開閉が容易になり、適切な水管理が可能になります。
農業は自然を相手にする仕事ですが、こうした小さな工夫の積み重ねが、美味しいお米へとつながるのです。
田んぼの草刈りをしないと、稲の生育が悪くなります。なぜなら、雑草が繁茂し、水や養分が稲ではなく雑草に吸収されてしまうためです。
例えば、代表的な田んぼの雑草であるタイヌビエやコナギなどが繁殖してしまうと、水や養分、日光までもが奪われてしまい、稲の収穫量は減少します。
また、雑草により風通しも悪くなるため、稲の病気が発生する原因にもなります。
引用元:アスグリ
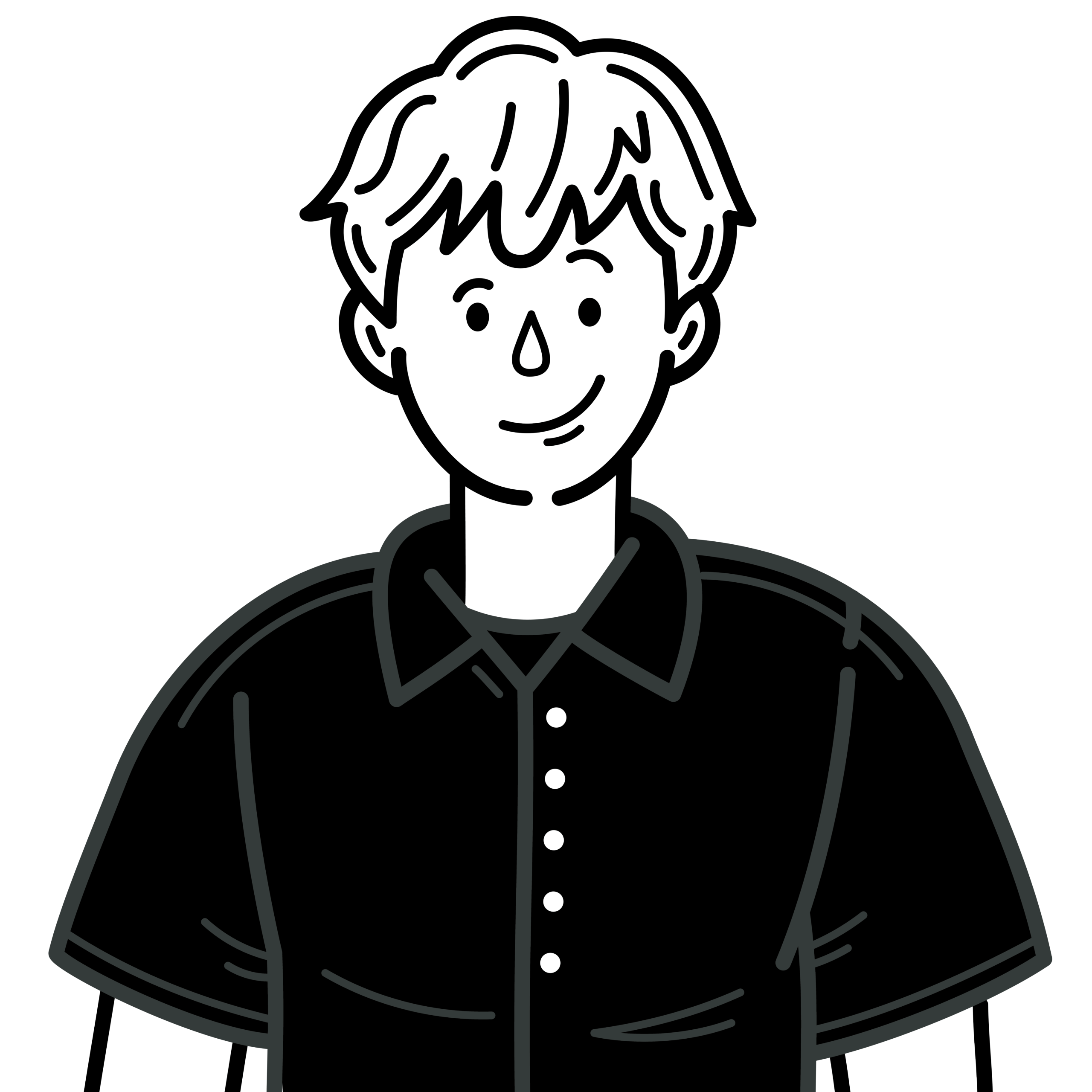
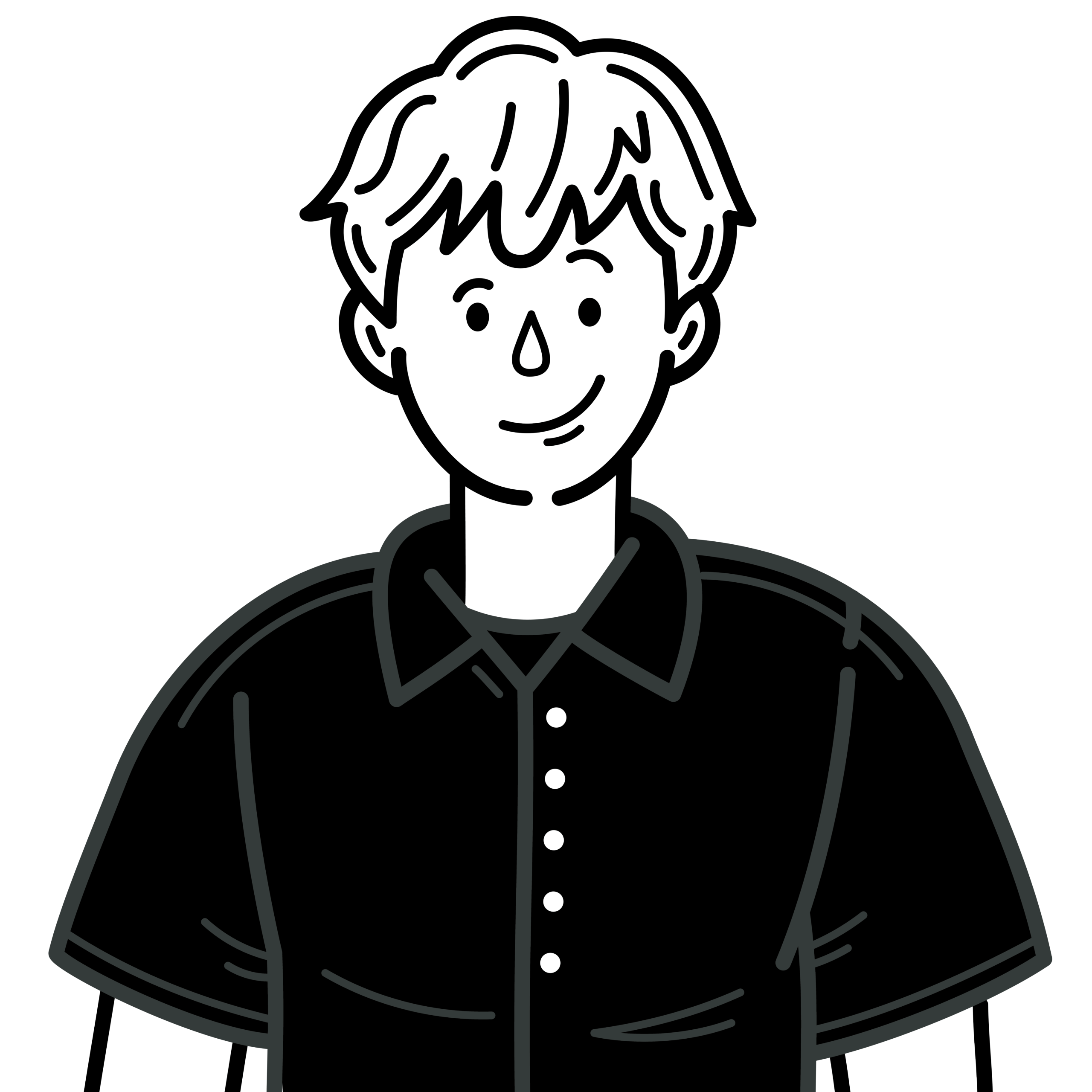
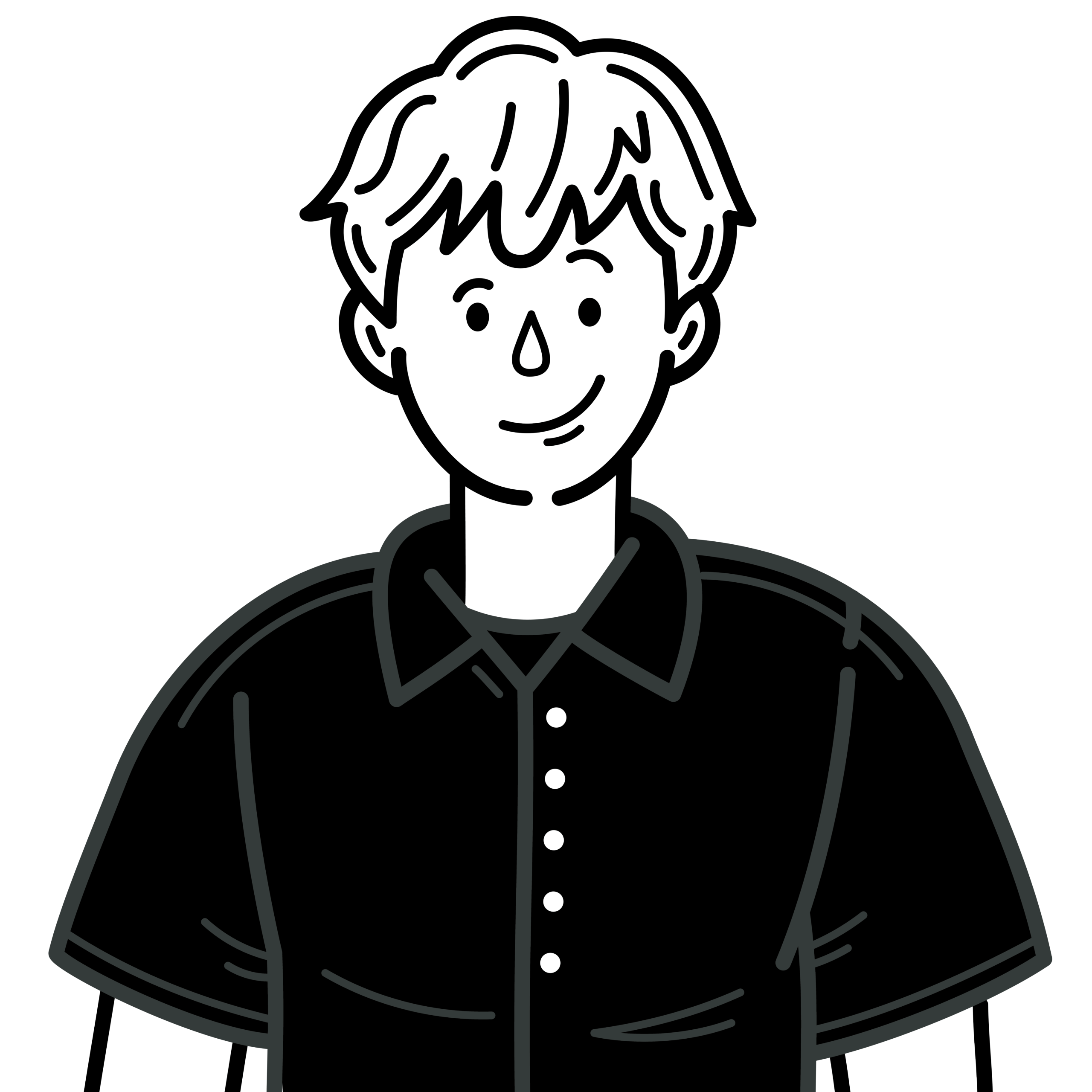
地道な作業には、単に見た目をきれいに保つこと以上の意味があります!
2. 追肥は「タイミング」が命


稲の生育段階に合わせて栄養を与える追肥(ついひ)は、お米の味や収量を決める重要な作業です。とくに、穂が出る時期の追肥は細心の注意が必要だと学びました。
茎ばかり伸びてしまうと「倒伏」の危険も
追肥のタイミングが早すぎると、茎の中の穂(この時点ではまだ液状)に栄養が回らず、茎ばかりが伸びてしまいます。その結果、稲が倒れやすくなる原因となります。一度倒れてしまった稲は、穂に十分に栄養が行き渡らず、お米の粒が未熟なままになってしまいます。これを防ぐためにも、穂にしっかりと栄養が行き渡るよう、稲の状態を日々観察し、ベストなタイミングを見極めることが非常に重要です。
祖父母から教わった「葉色(ようしょく)」のサイン
追肥のタイミングは、葉の色で判断します。祖父母からは「葉色が少し薄いかな、と感じたら追肥のサインだ」と教わりました。これは、稲が栄養を求めているサインです。長年の経験から培われたこの知恵は、まさに教科書には載っていない生きた情報です。僕たちの田んぼでは、このサインを見極めて追肥を行いました。追肥には「イネ用」の化成肥料を使います。この肥料は、窒素・リン酸・カリウムのバランスがとれた稲の生育に最適化されており、とくに窒素が重要な成分です。
3. 見過ごされがちな水管理!稲刈り直前の「水抜き」の重要性


田植え以降、ずっと水が張られていた田んぼ(中干し期間を除く)ですが、稲刈りが近づくと、ある重要な作業を行います。それが「落水(水抜き)」です。
なぜ稲刈り前に水を抜くのか?
この時期に田んぼの水を抜くのには、主に二つの理由があります。
一つ目は、稲を乾燥させるためです。稲刈りをする際に、稲穂の水分量が多すぎると、お米の粒が割れてしまう原因になります。稲刈り直前に水を抜いて、稲をしっかりと乾燥させることで、収穫時のロスを減らすことができます。
二つ目は、コンバイン(収穫機)の作業効率を上げるためです。水が残ったままの田んぼは、コンバインのタイヤが泥に埋まってしまい、作業がスムーズに進みません。最悪の場合、機械が動かなくなり、収穫作業が中断されてしまいます。稲刈りの数日前から水を抜くことで、田んぼの土が固まり、コンバインが安定して作業できるようになります。
僕たちの田んぼでは、稲刈りの14日ほど前から水抜きを始めました。この水抜き作業は、稲刈りをスムーズに行うための最後の準備であり、美味しいお米を最後まで守るための重要なプロセスなのです。
4. カメムシ防除は「籾が柔らかい時期」が決め手
近年、多くの農家さんが悩まされているカメムシ問題。僕たちの田んぼでも、稲刈り直前にカメムシが大量発生しましたが、被害を最小限に抑えることができました。その理由をこの章では紹介します。
稲が最も無防備になる時期を狙うカメムシ
カメムシは、稲の「出穂期(稲の穂がでる時期)」から「登熟期(籾がミルク状になる時期)」にかけて集中的に飛来します。この時期の籾は柔らかく、カメムシが養分を吸汁しやすいためです。被害を受けると、お米に黒い斑点が付く「斑点米(はんてんまい)」や、生育不良の「しいな(米粒が入っていない、または中身が未熟な状態)」が発生し、お米の品質が大きく低下してしまいます。斑点米は、見た目が悪くなるだけでなく、食味も落ちてしまうため、農家にとって深刻な問題です。
毎日田んぼを「覗く」ことの重要性
僕たちはこの出穂期を見逃さないよう、毎日田んぼに足を運び、稲の成長を「覗いて」いました。具体的には、茎を抜き、カッターで切り、穂が出てくるタイミングを図ります。そして、籾が柔らかい時期に入ったタイミングで、カメムシ防除の薬剤「アミスタートレボンSE」を散布しました。
おかげで、稲刈り直前にカメムシが発生しても、すでに籾が硬くなっていたため、大きな被害はありませんでした。
最後に
田植えから稲刈り直前までの約60日間、とくに印象に残った3つの出来事や学びをご紹介しました。
農業は害虫被害や天候、自然災害に左右される大変な仕事ですが、その分、やり方によっては非常にやりがいのある仕事です。個人的には、農業と一言で言っても、それぞれのスタイルや工夫があり、奥深さを感じています。
いよいよ稲刈りが始まりました。
今シーズンも残りわずかですが、精一杯田んぼと向き合っていきたいと思います。
もし、この記事を読んで「うちの田んぼではこうしてるよ!」といった経験談があれば、ぜひコメントで教えてください。








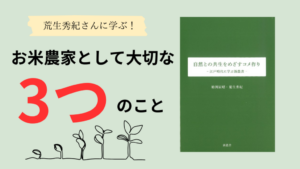
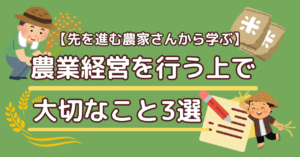
コメント